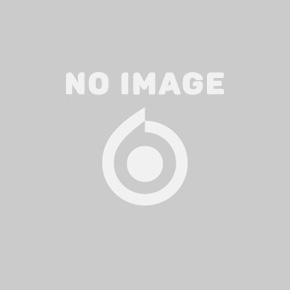まず大前提からお話ししますが、2030年の仕事については「国家財政の破綻」を抜きにして語っても意味がないと思います。
『10年後に食える仕事 食えない仕事』は、グローバル化によって日本人の働く環境にどのような影響が出るかを語った本です。
グローバル化による影響が伝わりにくくなってしまうため、ここにはあえて財政破綻の影響は加味しませんでした。
しかし実際は、このままでは国債暴落による財政破綻が起きることは確実です。
その場合、日本人の働く環境が財政破綻の影響を大きく受けることは間違いありません。
国債暴落とその顛末について、私は2011年に、週刊誌にシミュレーション小説「老人が泣き 若者は笑う」を発表しました。
その小説では2013年に国債が暴落することになっていますが、今は、東京五輪が開かれる2020年までは財政出動により暴落は起こらず、Xデイは2021年にやってくると考えています。
続く

日本の財政問題は、日本政府や行政機関が抱える財政上の問題のことです。
現在、日本政府の予算は、歳出(支出)が大きく歳入の約半分を国債発行による収入で占めています。
現在の日本政府が1000兆円の借金を背負っています。
日本は現在も将来も急速に高齢化が進んでいきます。すると、日本の強みである「貯蓄」というのが減ってきます。
日本全体で高齢化が進むことで社会全体の貯蓄額が減るということにつながるのです。
一方で働いている人は少ないですから、集められる税金というのは減っていく一方です。すると、政府が集められるお金が減っているのに、使わなければいけないお金は増えていくと言う状況になります。
すると、今は世界でも有数の大国である日本が発行した国債でも、信用は下がっていきます。
国債の多くを外国人が持っている状況で、国債が信用されない状況になると、ただでさえリスクを冒して日本の国債を持っている外国人は、容赦なく国債を手放し始めます。
国債を「売りたい」という人が増えてくると価格はどんどん下がっていきます。
このように価格が下がっていくと、国債を持っている日本人の投資家も日本の銀行も損失が出ることになります。
すると、損失を出したくないと考えた国内の投資家や銀行も国債を売り始めます。
すると、いよいよ政府が発行した借金を誰も買ってくれなくなります。
その頃には無駄を全て切り落としても日本政府は借金をしないとやっていけない状態なのに、誰もお金を貸してくれない、つまりこれが「財政破綻」です。